「頭痛・もの忘れ外来」もの忘れ外来について
2024年09月12日 お知らせ
令和6年6月より、頭痛・もの忘れ外来を開設いたしました。新しいアルツハイマー型認知症の薬ができて、治療方法もだいぶ変わってきました。頭痛・もの忘れ外来の診療内容の内、認知症についてご説明いたします。
目次
- 認知症の現状と原因について
- 新しい認知症の薬について
↳レケンビ(レカネマブ)の問題点
↳レケンビ(レカネマブ)による治療の流れ - もの忘れ外来の流れ
↳頭痛・もの忘れ外来の受診方法 - 入院について
↳地域包括ケア病棟
↳認知症ケアチーム
認知症の現状と原因について
Q: 認知症の患者数や状況について教えてください。
A: 認知症の患者数は2040年まで増え続けると言われています。2030年で523万人を超え、認知症予備群の方を合わせると1100万人くらいになります。
Q:認知症予備群とは、どのような方ですか?
A:MCI(軽度認知障害)と呼ばれる人たちで、正常と認知症を発症する境界に位置する人たちを言います。年に5%~15%が認知症を発症します。反対に年14%~44%は正常に回復します。
Q:MCI(軽度認知障害)の時期は、治るか?悪化するか?の微妙な時期ですね。 認知症になると脳内ではどのようになるのですか?
A:下のグラフの通り、6割から7割はアルツハイマー型認知症です。
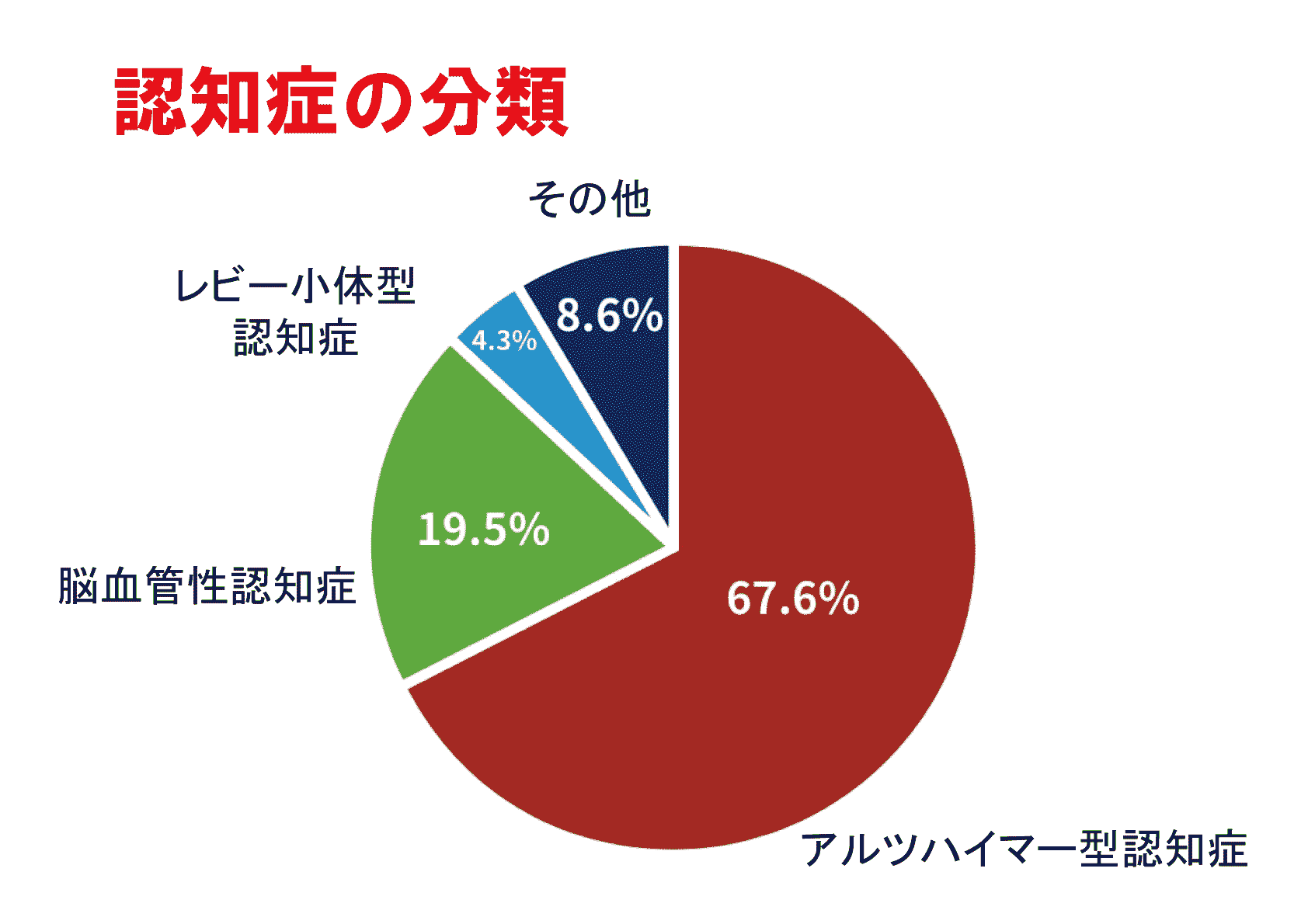
なぜアルツハイマー型認知症になるか?ですが、脳内の神経細胞の外側にアミロイドβが蓄積します。
1.アミロイドβ(Aβ)が神経細胞の外側に蓄積
そして ↓
2.タウたんぱくが神経細胞の内側に蓄積
そうなると ↓
3.神経細胞が壊されていく
↓
4.認知機能が失われていく
数十年かけて徐々に進行します。
Q:アミロイドβはいつ頃から溜まりだすのですか?
A: すでに40歳代からアミロイドβが蓄積し始めて、20年~30年経って70歳代で認知機能障害が出てきます。
新しい認知症の薬について
Q:最近報道されている新しい認知症の薬について教えてください。
A:今までは認知症を遅らせる薬はありましたが、アミロイドβに直接作用するものではありません。
レケンビ(レカネマブ)は全く新しいタイプの認知症の薬で、アミロイドβを除去する薬です。
朗報ではありますが問題点があります。
Q:レケンビ(レカネマブ)にはどのよう問題点があるのですか?
A: 副作用があることや、進行した認知症の人には使えない。金額が高額であるなどハードルがあります。
1.微小な脳出血 脳梗塞 脳浮腫、痙攣発作をきたすことがある。(副作用17%)
2.点滴製剤 しかも頻回に点滴投与が必要。 (2週間ごとに1回1時間の点滴を18ヶ月続ける)
3.手続きが煩雑。すぐには投与してもらえない。
4.対象はMCIから軽度認知症の人(認知機能検査で22点〜30点)。 進行した認知症の人には使えない。
5.軽度の認知症の人に投与するため あまり効果を実感できない。
6.金銭的に高額である。(年間298万円 保険適応あり)。
Q:レケンビ(レカネマブ)による治療の流れを教えてください。
A:脳神経外科、心療内科、放射線科等で検査を行います。アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度認知症と診断された場合、外部医療機関にてアミロイドPET - CT検査を行い陽性の診断されたら、レケンビ(レカネマブ)による治療を行います。
レケンビ(レカネマブ)による治療の流れ
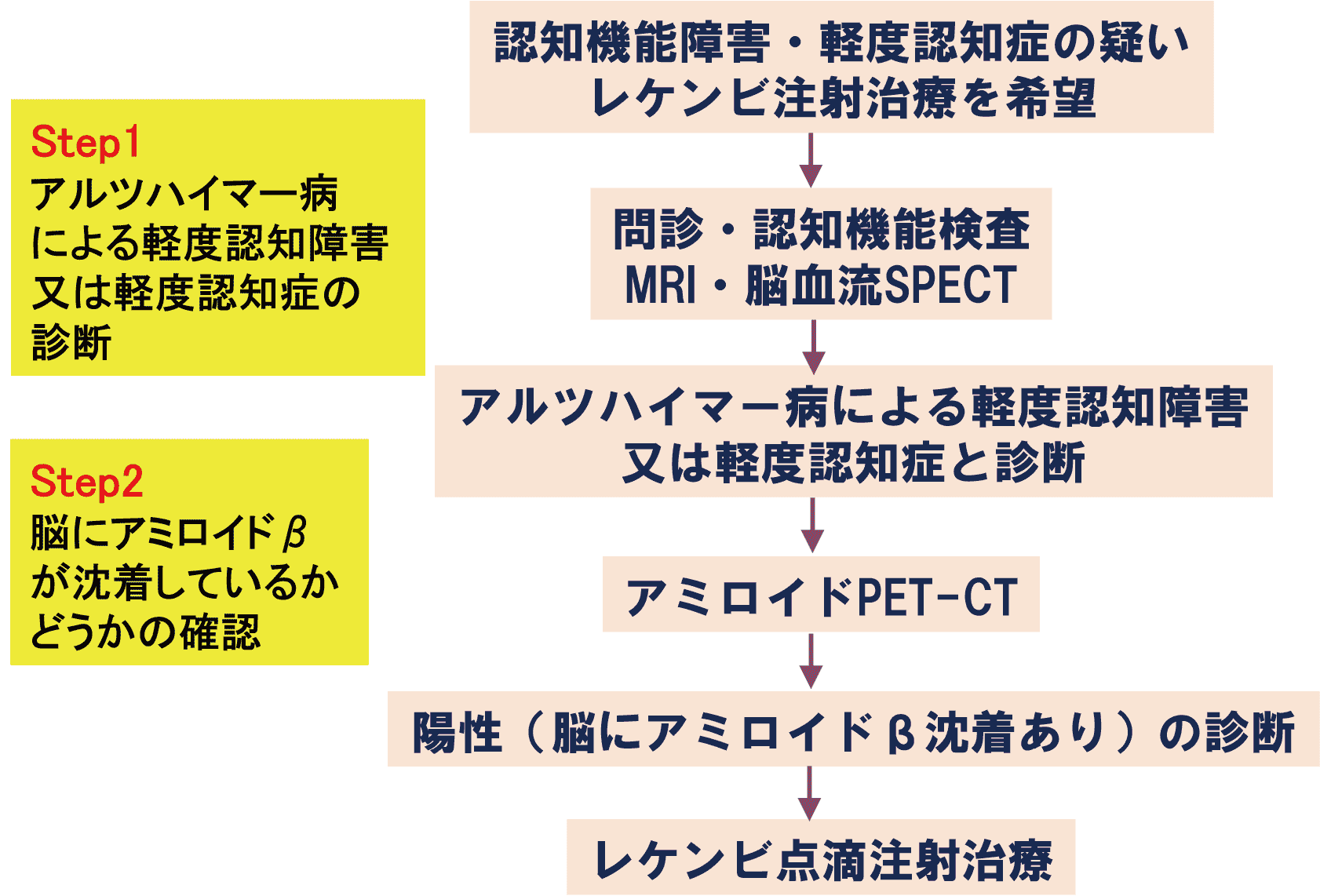
もの忘れ外来の流れ
Q:もの忘れ外来の診断・治療の流れを教えてください 。
A: 問診・診察から認知機能検査、内服薬の確認 を行います。そして血液検査、脳の画像診断等を行い、これらを総合して認知症になっているか?どのタイプの認知症か診断します。
認知症になっている場合、
薬物治療:認知症の進行を遅らせる抗認知症薬や徘徊など認知症の周辺症状に対しての薬物治療を行います。
生活指導・介護指導 施設・サービスの紹介:患者さんやご家族の生活・介護に関わるアドバイス。デイサービスなど介護サービスやグループホームなど施設の紹介をいたします。
もの忘れ外来のの流れ
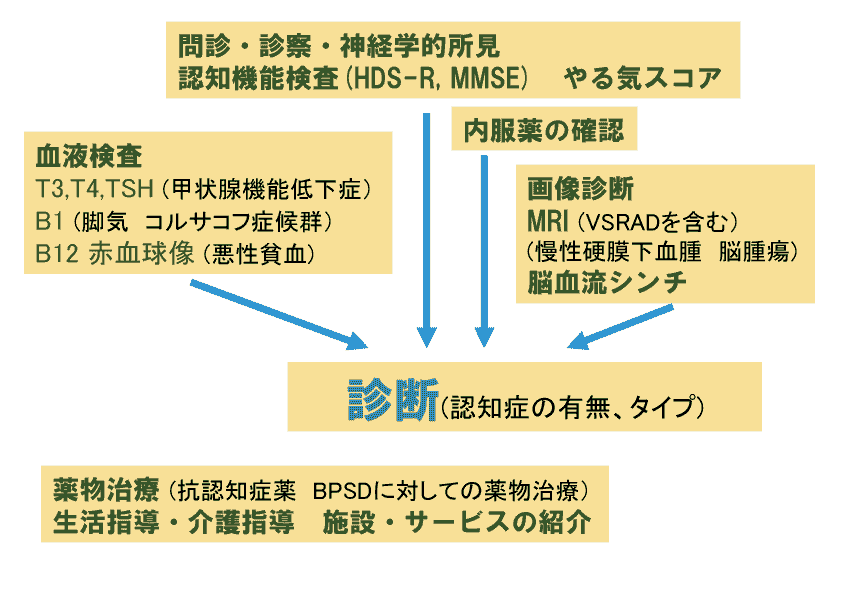
脳血流シンチグラフィ
脳は血流により運ばれたブドウ糖や酸素によって活動しています。多くの脳の病気は、血流の異常を伴っています。定量解析によって、脳血流のわずかな変化を見つける検査です。認知症などの解析診断にも実施されます。検査時間は1時間程度になります。
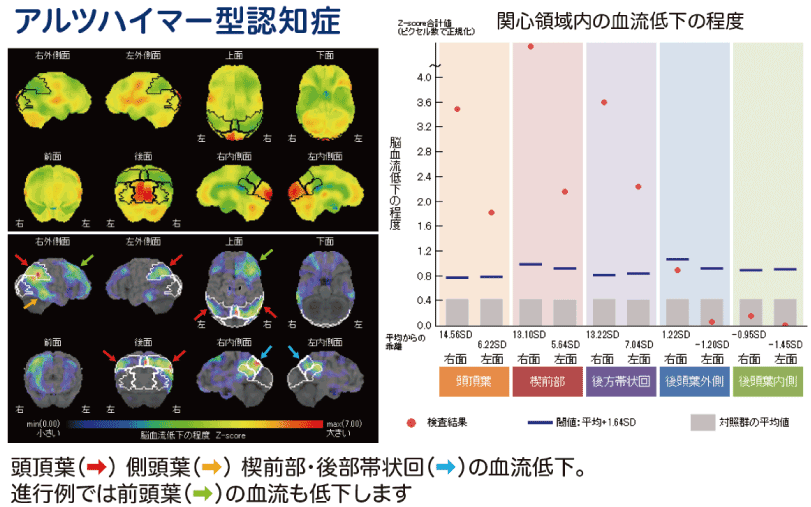
Q:頭痛・もの忘れ外来へ受診する方法を教えてください 。
A:気になる方は、ぜひ、かかりつけの先生にご相談下さい。
当院では病診連携(「かかりつけ医」クリニック・開業医との連携)を進めています。
当院での受診をご希望の方は、できる限りかかりつけ医やホームドクターからの紹介状をご用意のうえ、予約をお取りになってからご来院ください。
入院について
地域包括ケア病棟
当院では病診連携(「かかりつけ医」クリニック・開業医との連携)を進めています。
当院での受診をご希望の方は、できる限りかかりつけ医やホームドクターからの紹介状をご用意のうえ、予約をお取りになってからご来院ください。
東5階病棟は、地域包括ケア病棟です。主に退院支援を行なう病棟として、患者さんとご家族の思いを大切にした看護ケアの提供を行なっています。入院中には、患者さんの持てる力を引き出す関わりとして、生活リハビリや内服の管理行動の支援を行なうこと、高齢患者さんの認知機能の低下を予防する関わりなどに力を入れています。「多職種で考える退院支援」を病棟目標とし、常に情報共有しながら、患者さんが望む退院後の生活に"つなぐ"ことが出来るよう地域との連携を大切にしています。
地域包括ケア病棟についての詳細は、下記リンクボタンにてご覧ください。
認知症ケアチーム
認知症の患者さんは、身体の不調に加 え、入院に伴う環境の変化に適応しにくいた め、混乱をきたしてしまう場合があります。 家族にとっても、患者さんが混乱している姿 を見ることは辛いことであり、不安も大きく なります。
当院では、認知症の患者さんや認知機能が 低下した患者さんが、安心して療養生活を過 ごすことができ、治療を円滑に受けられるよ うにサポートしていくことを目的に、令和6 年4月に認知症ケアチームを結成しました。 そして、5月より認知症ケア回診を開始して います。
認知症ケアチームについては、下記リンクボタンにてご覧ください。

